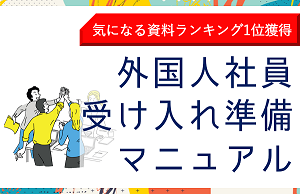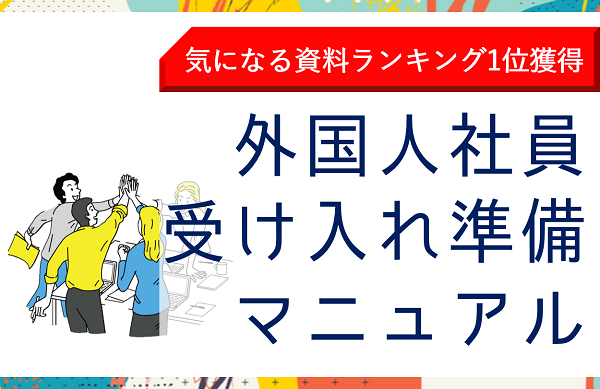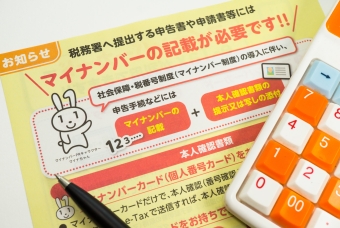現在、日本国内にはさまざまな国から来た人々が暮らしており、国民性や日本に居住するエリアや人数には傾向があります。本記事では、日本に住む外国人の割合が多い国のトップ5を紹介し、その国の方を採用する場合に企業が押さえるべきポイントや注意点を解説します。
外国人採用を検討している企業者や、日本での国際的な人材の流れに興味がある方は必見です。本記事を参考に、多様な人材を活用するためのヒントを知り、スムーズな採用・雇用につなげましょう。
100社以上の声から生まれた外国人採用の基礎資料!
- 新卒・中途の母集団形成がうまくいかない
- 就労ビザ申請の方法がわからない
- 採用後の社内体制整備の方法がわからない
などのお悩みを抱えている方必見の外国人採用の基礎資料です。
日本に住む外国人の多さはどのくらい?国別ランキングTop5

法務省が発表した、2024年(令和6年)の外国人入国者数・日本人出国者数等の推移によれば、
日本に住む外国人の多さは、中国>ベトナム>韓国>フィリピン>ブラジルの順となりました。
法務省のデータでは、香港とそれ以外の中国の人数が分けて算出されていますが、これを合計すると、日本に住む外国人で割合が最も多いのは中国人となるでしょう。
Top5にランクインしている国の人の特徴を、以下にまとめました。
※在留カード及び特別永住者証明書上に表記された国籍・地域の数
1位:中国(香港を含む)|844,187人(前年比+22,349人)
日本に移住した中国人は特にIT関連のビジネス、貿易、飲食業で活躍し、中国系企業に就職する人が増えています。また、日本の大学や専門学校に留学し、そのまま日本で働くケースも一般的です。
東京・池袋、大阪・難波、横浜の中華街などですでに中国人コミュニティが形成されており、日本語が流暢でなくても中国語が通じる環境が、他国に比べると多い傾向にあります。
飲食業では中華料理店の経営が多く、近年は火鍋やスイーツ店が人気です。日本にいても、中国語が通じる環境が多いため、言葉の壁に課題を感じる人も多いほか、日本の企業などに就職する場合は労働文化の違いなどにもギャップを感じることがあります。
2位:ベトナム|600,348人(前年比+35,322人)
ベトナム人の来日目的は、主に技能実習や留学、就職が目的であるケースが多いです。特に製造業や建設業、介護分野で働く人が増えており、技能実習生として日本に滞在することが一般的です。
また日本での留学を経て日本で就職する人も増えており、ITやエンジニアリング分野に進出するケースも見られます。ベトナム人のコミュニティは、東京や大阪、名古屋などに広がっており、ベトナム料理店やカフェが人気です。
日本ではベトナム語を話せる人が少なく、来日したベトナム人本人が日本語をある程度話せなければ、言語の壁にぶつかりやすく、日本文化への適応も時間がかかる可能性があります。
しかし、日本語を学びながら仕事をする人も多く、勤勉で日本への適応力が高い人が多いと言われています。
3位:韓国|411,043人(+前年比887人)
日本に住む韓国人は、自分より前の世代(父母や祖父母)の代から日本に住む在日韓国人と新規移住者に大きく分けられます。在日韓国人は歴史的背景を持ち、日本に定住している人が多いのに対し、新規移住者はビジネスや留学、結婚を目的に来日している傾向が多いです。
実際に、日本人と韓国人の結婚率は増加傾向にあり、統計庁が発表している「婚姻・離婚統計(2023年)」によれば、韓国人男性と日本人女性の婚姻件数は前年比40.2%となりました。
その他にもITなどのビジネス関連で移住する人も多くいます。在日韓国人は生活に困らない程度の日本語をすでに習得しているケースが多く、新規移住者も日本語を学ぶ人が多いため文化適応も比較的スムーズですが、就職やビザ取得で苦労するケースもあります。
韓国人を採用する場合、企業側は適切なビザが取得できるよう、採用活動時や雇用契約締結時にしっかりとサポートする必要があるでしょう。
4位:フィリピン|332,293人(前年比+10,247人)
フィリピンから日本へ移住した人は、介護やサービス業、製造業で働く人が多い傾向にあります。そのほかにも留学や技能実習生として特定技能ビザを取得して生活する人々も増えています。
日本語を学びながら働く人が多く、言語や文化の違いに直面することもありますが、フィリピン人はコミュニケーション能力が高い人が多い傾向にあり、柔軟に適応するケースも多いです。
日本のフィリピンコミュニティは、東京や大阪、名古屋に多く、その地域にはフィリピンの料理を扱う飲食店も多いです。
5位:ブラジル|212,325人(+前年比485人)
ブラジル人が日本へ来る目的として、主に就職、再移住、家族の結びつきなどがあります。
製造業や自動車業界で働くブラジル人が多く、日系ブラジル人(過去にブラジルへ移住した日本人の血縁を持つ人々)が多く来日しています。彼らは日本で働くための技術や知識を持っており、また家族を呼び寄せて生活を安定させることが一般的です。
日本語の習得には時間がかかることもありますが、ブラジル人コミュニティは東京や大阪、愛知県などに広がり、ポルトガル語を使う環境が整っています。
100社以上の声から生まれた外国人採用の基礎資料!
- 新卒・中途の母集団形成がうまくいかない
- 就労ビザ申請の方法がわからない
- 採用後の社内体制整備の方法がわからない
などのお悩みを抱えている方必見の外国人採用の基礎資料です。
在日外国人が多い都道府県・ビザの種類ランキング

在日外国人が多い都道府県のTop5と、取得するビザの種類で多いものを紹介します。
在日外国人が多い都道府県は、東京都
在日外国人数が最も多いのは東京都で、70万人以上に上ります。これは全国の19.6%を占め、その次に愛知県、大阪府、神奈川県、埼玉県と続きます。
外国人労働者の求人の多さや在日外国人のコミュニティが多くなるため、やはり東京に住む外国人は多いです。また、その次に愛知県に在留外国人が多い理由は、灯篭度生活環境が整っていることが要因です。
愛知県労働局のHPによると、令和5年10月1日時点では愛知県の最低賃金は1,027円と、他県と比べると高い傾向にあるほか、外国人受け入れに前向きな、トヨタ系などの製造業が中心の商圏となっていることも要因の一つです。
在日外国人が取得することが多いビザ
在日外国人が日本で働く場合取得する割合が多いビザの種類は「技術・人文知識・国際業務」ビザです。これは、本人の学歴、またはこれまでの職歴と、日本で仕事をする際の業務内容との関連性があることが要件となります。
本人の専門的な知識やスキルなどを活かせる業務内容ではないと判断されてしまうと、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格は取得できません。
その次は特定技能・技能実習・介護と続きます。
100社以上の声から生まれた外国人採用の基礎資料!
- 新卒・中途の母集団形成がうまくいかない
- 就労ビザ申請の方法がわからない
- 採用後の社内体制整備の方法がわからない
などのお悩みを抱えている方必見の外国人採用の基礎資料です。
在日外国人採用時に、企業が気を付けるポイント

特定技能を持つ外国人を受け入れる場合
外国人が取得する就労ビザのうち、「特定技能」は2019年4月に創設された新しい在留資格です。
日本国内で、今後人手不足が深刻になると懸念される特定産業分野(16分野)において、即戦力となる外国人材の就労を可能にします。
特定技能は、「特定技能1号」と「特定技能2号」の2つがあり、1号は16分野、2号は介護分野以外の11分野が指定されています。これらの分野は、特別な育成などを受けなくても即戦力として一定の業務をこなせる水準であることが要件です。
また特定技能を持つ外国人を受け入れるためには、企業として以下の要件を満たす必要があります。
- 特定技能を持つ外国人を受け入れる場合に企業に必要な要件
企業の業界が特定産業分野である
特定技能外国人を雇用する前に対象の協議会へ加入している必要がある ※2024年6月14日から
特定技能外国人1号への支援計画を策定し、雇用後に支援を行う
在日外国人が日本にいる背景を理解する
日本に住む外国人の中にはさまざまな事情があって来日した人も多くいます。日本が好きで移住してきた人はもちろんのこと、自国で働くよりも高い給料をもらい、家族へ仕送りがしたい、日本で最先端の技術を学び、自国へ戻って仕事を発展させたい、といった希望を持つ人も少なくありません。
企業が外国人を採用する場合、とくにビザを取得する必要がある場合は、なぜ日本で働いているのか、その背景も多少なりとも考慮する必要があるでしょう。
一度は採用されたのに、ビザが取得できずに日本で働けなくなってしまうとその人はまた新たに仕事を探したり、帰国を余儀なくされてしまうケースもあります。
外国人採用を検討する場合は、受け入れ企業側の準備も事前にしっかりと行うことが重要です。
100社以上の声から生まれた外国人採用の基礎資料!
- 新卒・中途の母集団形成がうまくいかない
- 就労ビザ申請の方法がわからない
- 採用後の社内体制整備の方法がわからない
などのお悩みを抱えている方必見の外国人採用の基礎資料です。
在日外国人採用、企業が果たすべき役割とは

法務省のデータによれば、コロナ禍を経て、日本に住む外国人は増加傾向にあります。中国をはじめ、アジア諸国から、日本での技術取得や高い収入を得たいという目的で来日する人も多くいます。
在日外国人を企業が採用する場合は、ビザ取得に関して手厚いサポートを行う必要があるほか、特定技能を持つ外国人を受け入れる場合には、企業側にもいろいろな準備が必要です。
採用する外国人がなぜ日本で働くのか、その背景も考慮したうえで、採用に関する準備を進めていきましょう。

 03-6367-2041
03-6367-2041